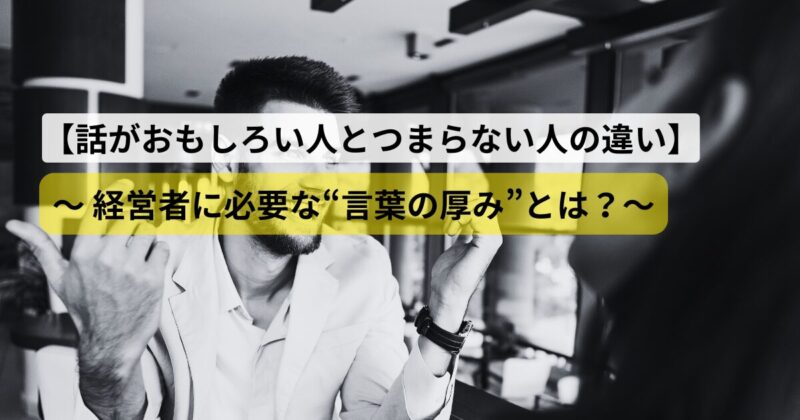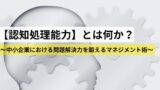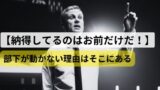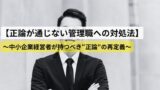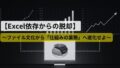中小企業の経営者や管理職にとって、社員との対話や社内コミュニケーションは日々の業務における要である。だが、自分の話が「伝わっていない」「響いていない」「つまらない」と感じた経験はないだろうか?面白い話し手とそうでない人の違いは、性格や口調ではない。「知識の厚み」と「本質を語る力」である。経営者として信頼を得て、組織を前進させるには、受け売りではない“自分の言葉”を持つことが重要だ。本稿では、経営を動かす“言葉の厚み”の正体に迫る。
「つまらない話」が生まれる背景とは?
会議や雑談で、「それ、テレビで聞いたな」「で、何が言いたいの?」と感じさせてしまう話がある。これは話し手の知識や意図の浅さに起因する。
TVやネットで得た知識を“そのまま話す”危うさ
多くの経営者が、話題のニュースやビジネス本で得た知識を、そのままの言葉で部下に伝えようとする。しかし、これは「自分の意見」ではなく「誰かの考えを繰り返しているだけ」であり、聞き手にはすぐに見抜かれる。「どこかで聞いた話だな」と思われた時点で、言葉は響かなくなる。

話の核心が見えないと「で、何が言いたいの?」となる
話に結論がない、もしくは論点がぶれる場合、聞き手は混乱する。原因は多くの場合、話し手自身が「何を伝えたいか」が明確になっていないことだ。浅い理解のまま話すと、聞き手にとっては時間の無駄に感じられてしまう。
知識はあっても“本質”を外していると話は浅くなる
表面的な情報や数字を並べても、聞き手の心には残らない。「その数字の意味は?」「それが自社にどう関係するのか?」という“橋渡し”がなければ、知識はただの雑学で終わる。話が面白くなるためには、本質を掴み、それを自分の言葉で語る必要がある。
「話がおもしろい人」の3つの共通点
魅力的な話をする人には、明確な共通点がある。それはテクニックではなく、思考の深さにある。
情報を一度“自分の頭”で考え直している
情報を得た時、鵜呑みにせず「なぜそうなるのか?」「うちの会社に当てはまるか?」と一度咀嚼する。だからこそ、話に“自分の意見”が乗り、厚みが生まれる。受け売りではなく、実感を伴った言葉は、聞き手にとっても信頼できる情報となる。
比喩や具体例で伝えるから“イメージ”が湧く
たとえば、セキュリティ対策の話を「家の鍵を閉めずに外出するのと同じ」と例えることで、一気に理解が深まる。面白い話し手は、こうした比喩や体験談を織り交ぜることで、聞き手の頭に映像を描かせることができる。

聞き手が「なるほど」と納得できる“本質”を突いている
表面的な話ではなく、「なぜこの話が重要なのか?」という本質に触れることができる人は、話の中に“芯”がある。経営者であれば、「この方針を取る理由」を、社員の目線に立って噛み砕いて話せるかが問われる。
ダイエット理論から学ぶ“知識の罠”
世の中には「これさえやれば成果が出る」という理論があふれている。ダイエットも、経営も、情報も…あらゆる分野に“正解らしきもの”が語られる。しかし、知識は万能ではない。「その通りにやったのにうまくいかない」のはなぜか…その落とし穴を、ダイエット理論から学ぶ。
「万人に効く知識」は存在しない ― 体質が違えば結果も変わる
「朝食抜きで痩せる」「糖質制限で脂肪が燃える」「16時間断食でオートファジーが活性化」…こうしたダイエット法は、ネットやテレビ、書籍でも定番の話題だ。しかし、同じことをしてもAさんは痩せて、Bさんは体調を崩す。その差はどこにあるのか?
それは、民族的な体質・生活習慣・文化的背景の違いにある。欧米人と日本人では腸内細菌も代謝のスピードも異なる。「欧米の研究で効果あり」と言われても、それが日本人に最適とは限らないのだ。知識は普遍ではなく、“条件付き・何らかの前提があっての真実”であることを見落としてはならない。

経営の世界でも同じだ。業種も、社員構成も、地域性も異なる中で「このやり方が成功したから」と真似をしても、同じ結果にはならない。体質が違えば、処方箋も変わる。これは経営にもそっくり当てはまる。
「犬にドッグフード、猫にキャットフード」 ― GAFAの真似は毒にもなる
仮にダイエット成功者が「俺はドッグフードで健康になった!」と言ってきたとしても、猫にそれを勧めるだろうか?普通は「それは犬用だからダメ」と言うはずだ。だが、経営となるとどうだろう。GAFAや外資系企業のマネジメント手法、シリコンバレー式の評価制度、海外MBAの理論などが「良い」とされると、それを日本の中小企業にそのまま導入しようとする。
しかし、組織文化も人材層も違う企業に、同じエサ(手法)を与えれば、拒否反応が起きるのは当たり前だ。GAFAは自由度が高いように見えて、実は「優秀な人しか採らない」という前提の上に成り立っている。誰でも採用し、教育し、組織で支え合っていく中小企業がそのやり方を真似すれば、当然、崩壊する。
猫にドッグフードは通用しない。自社の体質を見極め、自社用の“栄養学”を設計できる経営者だけが、真に知識を活かすことができる。
他社の成功事例は「レシピ」ではなく「ヒント」として扱え
よくある失敗が、「あの会社はSNSマーケティングで売上が3倍になった」「リモートワークを導入して離職率が下がった」という事例を見て、「じゃあ、うちでもやろう」とすぐに飛びついてしまうパターンである。
だが、その事例には“背景”がある。
・リーダーのキャラクター
・社員のITリテラシー
・顧客層の属性
・市場タイミング
これらがそろって初めて成功したことが、そっくりそのまま別の会社で通用するわけがない。
つまり、他社の成功事例はレシピ本ではなく“食材選びのヒント”くらいに考えるべきなのだ。料理には「味見」が必要なように、経営にも「自社に合うかどうかの吟味」が必要だ。自社の強みと弱み、社員の特性、業界の動き…すべてを踏まえてカスタマイズしなければ、“知識の毒”にさえなり得る。
🔎補足視点:「知識=リスク」になる時代
知識は武器になる。しかし、使い方を誤れば“誤爆”にもなる。
特に経営者の言葉は、社員にとって方針であり、行動指針である。薄っぺらい知識やどこかで拾った流行語をそのまま使えば、「また始まったよ」「それ、前の会社でやってたな…」と社員の冷めた視線を招くだけだ。
大切なのは、「この知識は、自分の会社にとって何を意味するのか?」を自分で解釈し、自分の言葉で語る力。
話の厚みは、知識そのものではなく、その知識をどれだけ“自分で咀嚼したか”で決まる。
話をおもしろくする“知識の磨き方”
伝わる話をするには、知識の仕入れ方よりも“磨き方”が重要である。
情報を受け取ったら「なぜ?」と問い直す
ニュースや講演で得た情報も、「それって本当か?」「自分の業界ではどうなる?」と立ち止まって考える。知識を疑う姿勢が、言葉に深みを与える第一歩だ。

学んだことを“自分の言葉”に翻訳してみる
理解したつもりでも、それを自分の言葉で再現できなければ意味がない。「誰かに説明できるレベル」にまで噛み砕くことで、知識は血肉になる。会議で話す時も、“自分の言葉”で伝えることで納得感が生まれる。
数字・体験談・比喩で“説得力”を補強する
知識の裏付けとして、具体的な数字や自分の体験を交えることで、話は一気に現実味を帯びる。抽象論だけでは響かない。例えるなら、道具だけ渡して「料理して」と言うようなもの。調理の仕方=言葉の使い方を伝えることで、伝達力は何倍にもなる。

まとめ ― 経営者こそ「言葉の厚み」で人を動かせ
経営者にとって「話が面白い」と言われることは、単なる話術の問題ではない。自分の言葉で話し、本質を突き、相手に響かせる力は、経営の実行力にも直結する。「知識+思考」から生まれる厚みのある言葉は、社員を動かす力を持つ。口先だけの指示ではなく、思考を深めた“言葉の武器”を持つことこそが、経営者のリーダーシップであり、信頼構築の要である。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。