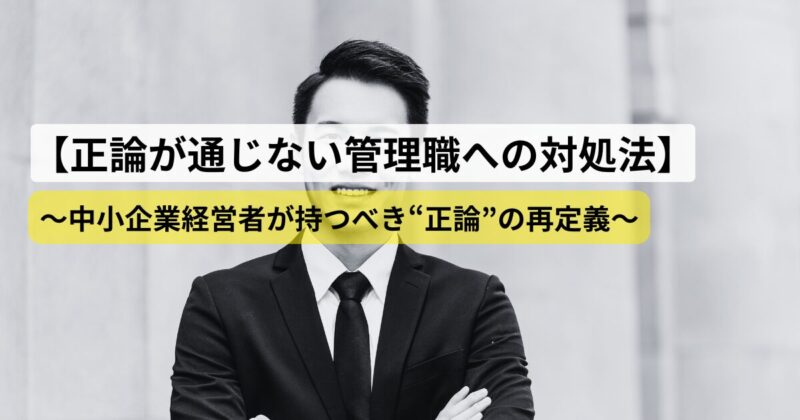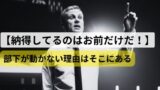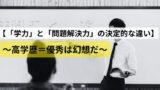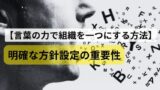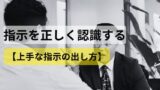中小企業の現場でよくある「正論が通じない管理職」という課題。社員の不満だけでなく、経営判断を曇らせる原因にもなり得るこの問題は、単に“人間関係のすれ違い”では済まされない。正論を語る側、受ける側、それぞれの立場と心理構造を理解しなければ、的外れな対応になってしまう。本記事では、「正論が通じない管理職」という難題に対し、経営者自身が持つべき視点、陥りやすい誤作動、そして“通じる言葉”へと翻訳する方法まで、実践的に解説する。読了後には「正論とは何か?」の認識が一段階深まるはずだ。
正論とは何か?|経営現場での“正論”の定義
中小企業の経営現場における「正論」とは、単なる理想論や一般論ではなく、「企業としての目的達成に必要な行動原則」と定義すべきだ。単に“正しいことを言う”のではなく、“組織を動かす実効性ある提案”として成立して初めて、それは経営における意味のある正論となる。
正論は「事実」に基づいた“目的合理性”である
正論とは、論理的に正しく、社会的にも常識とされる意見である。しかし、経営の現場では、理論上正しいだけでは不十分だ。中小企業における正論とは、「今、この現場で、この組織の目的に照らして最も合理的である」ことが前提でなければならない。たとえば、「顧客第一で動くべきだ」というのは確かに正論だが、社内の体制が追いついていなければ現場は混乱するだけだ。つまり、正論には“文脈”が不可欠である。
「一般論」は通じない場面がある
世の中のベストプラクティスが、すべての会社にフィットするわけではない。たとえば、「マニュアル整備をすべき」という正論も、リソース不足の現場ではかえって負担となる。このように、正論を掲げるだけでは逆効果になるケースも多い。経営における正論は、“正しい”だけでなく“機能する”ものでなければならない。
そして、ここで経営者や管理職がもっとも気をつけるべきなのは、「正論を言うだけでやっているつもりになっている状態」である。
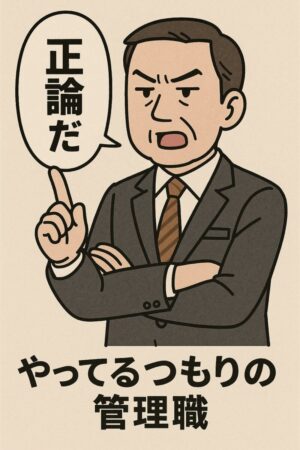
正論の落とし穴|“語るだけ”で満足してしまう人たち
中小企業の現場では、「正論を語る人」ほど、実は何もやっていないという現象がある。言い換えれば、「言ったら終わり」「考えたら役割は果たした」という錯覚である。
たとえば、「これからはDXが必要だ」「マニュアル整備を進めよう」「顧客起点で考えるべきだ」など、もっともらしい正論を語る人がいる。しかし、その人は、具体的にどう進めるのかを考えていないし、実行の責任も持たない。ただ“言う”だけだ。そして「実行は現場の仕事」と他人事にする。
さらに厄介なのは、「やっていないこと」を「やったこと」にカウントしてしまう傾向だ。

セミナーに参加した、資料を調べた、誰かに提案した…これらは行動ではあるが、成果ではない。アウトプットも改善もされていないのに、「やったことがある」「考えていた」として実行済みを主張する。しかも、そこで得た情報を“自分の意見”として語り、「俺は知っている」「考えている」と自己評価を上げる。
これは、AIが数秒で出力できるレベルの知識を、さも“経営的判断”のように語る時代錯誤でもある。にもかかわらず、自分は情報感度が高いと思い込んでいる。「言うことは立派だが、何も生まれていない」。これが現場の冷静な評価である。
このような“正論ごっこ”が組織に蔓延すると、
- 誰も責任を取らない
- 実行は丸投げ
- 結果は曖昧
という状態が常態化する。最悪なのは、こうした人間が「俺が考えた。お前たちはやればいい」と本気で思っている点である。そこにリーダーシップも責任感もなく、ただの評論家的自己満足があるだけだ。
経営における正論とは「現実を前にした判断の軸」
このような“語るだけの正論”が蔓延している現場に必要なのは、「現実を動かす視点」だ。正論とは、他者を論破するための武器ではなく、現場で実行されるための“翻訳可能な判断基準”でなければならない。
本当の正論とは、
- 「やる」覚悟を持った言葉
- 具体的なアクションに落とし込める提案
- 結果に責任を持つ構え
この3つが揃って初めて意味を持つ。
単なる知識、口先だけの意見、誰かに“やらせる前提”の正論は、もはや通じない。現場を動かしたいなら、“自ら動く意志”が込められた言葉を持つべきだ。そこにこそ、経営者が発するべき真の正論が存在する。
なぜ正論が通じないのか?|心理と立場の構造
正論が通じないのは「理解力の問題」ではなく、「心理と立場」の壁があるからだ。
立場が違えば“見える景色”が違う
経営者の視点と管理職の視点はそもそも異なる。経営者は全体最適で判断しがちだが、管理職は現場や部門の部分最適で動いていることが多い。正論が衝突するのは、この視野の違いによるものだ。たとえば「今すぐ変革すべきだ」という正論も、現場の負荷やスキルが追いついていなければ、現場からは「空論」に映ってしまう。
「正論=否定」と受け取られる心理作用
人は自分のやり方を否定されたと感じたとき、内容の正しさよりも感情的反発が先に立つ。正論をぶつけた瞬間、相手は「自分が責められている」と感じてしまう。この感情の壁が、対話を不可能にしてしまう。内容に納得していなくても、「黙って従うふり」をして、実際には何も動かないという事態が発生する。
管理職には「自尊心」がある
正論が通じないのは、管理職の能力不足ではなく、“役職に付随する自尊心”が原因であることが多い。「わかっていないわけじゃない」「そんなことは百も承知だ」と思っていても、自分のやり方を変更するのは“負け”だと感じてしまう。そのため、正論を突きつけられるほど、態度は硬直化する。
正論を“通じる言葉”に変える方法
正論をそのまま語っても、現場には通じない。必要なのは、“伝わる形”に変換する努力である。経営者や上位職には、“翻訳責任”があると捉えるべきだ。
論理よりも「納得感」を優先する
論理的に正しい内容でも、「それが自分にどう関係するのか」が理解できなければ現場は動かない。「なぜ今これをやるのか」「やったらどう良くなるのか」という感情や利得の視点を丁寧に添えることが必要である。
例えるならば、経営者の言葉は「設計図」である。だが、設計図だけでは誰も家を建てられない。それをどう形にし、どう使うかまでガイドすることが“翻訳”だ。
資料化=“逃げ道を塞ぐ”ための指示
伝えたい内容があるなら、必ず“資料”という形でアウトプットさせるべきだ。これは「検討中」「考え中」といった曖昧な逃げを封じるためのマネジメント技法である。文章化・図解化された資料には、必ず中身が問われる。
そして、その資料を使ってプレゼンや説明をしてもらう。部下やチームがその説明を聞き、以下のような反応をするかをチェックすればいい:
- 「つまり、どうすればいいのか分かりません」
- 「それって具体的に何をするんですか?」
- 「いつまでに、誰が、何を?」
もしこうした質問が出た時に答えられないなら、中身がない、考えていない、翻訳できていないことが明白になる。
これは経営者が指摘するまでもなく、現場の“純粋な理解不足”が暴いてくれる。立場ではなく内容の問題として白日の下に晒される。
誤魔化せない構造を作ることで、無責任を是正できる
この仕組みの優れた点は、本人の誠実さや能力の欠如が、自然と可視化されていく点にある。説明の内容が薄い、論理が飛躍している、成果と結びつかない…そうした問題点が、部下からの質問や違和感で浮かび上がる。
これに対し、説明する側が
「伝わらないのは相手の理解力がないからだ」
と責任転嫁すれば、その瞬間に自己否定に陥る。
なぜなら、部下に伝えられない=指導力がない=マネジメント職として不適格、という構図が成り立つからだ。自尊心がある人間ならば、この構造には耐えられない。
だからこそ、
- 「翻訳せよ」
- 「資料にせよ」
- 「説明責任を果たせ」
という指示は、“実行できるかどうか”を明確に可視化するテストとして非常に有効なのだ。
そして沈黙するか、退くか、変わるか
このような工程を経て、自らの実力不足を理解した者は、いずれ三つの選択肢に迫られる:
- 変わる(努力し、責任を引き受ける)
- 沈黙する(余計な口出しをしなくなる)
- 退く(ポジションに自ら見切りをつける)
どれを選ぶにしても、組織としては前進である。正論ごっこを排除し、アウトプット責任を明確にする構造こそが、真の改善である。
経営者が持つべき「正論の再定義」
“通じない”ことを前提に、経営者は正論の再定義を行わなければならない。
「正しさ」と「伝わりやすさ」を両立せよ
本当に正しいことを実現するには、「伝わる形」で語らなければならない。つまり、経営者は“翻訳者”であるべきだ。組織の理念や合理的判断を、現場の文脈に落とし込める力が求められる。それが経営者にしかできない役割であり、リーダーシップの核心である。
正論は「問い」として使え
正論を“答え”として提示すると、対話は閉じる。しかし、正論を“問い”として投げかければ、対話が始まる。「どうしたらこの課題をクリアできるか?」「何が障壁になっているのか?」といった問いに変換し、相手の思考を引き出すことで、正論が“共通の目的”として機能しはじめる。
“理”を通すのではなく、“理”を伝える
「筋が通っている」ことと「納得される」ことは別物である。経営者は、正しさを押し通すのではなく、相手の中に“育てる”視点を持たなければならない。時間がかかっても、共に理解を育むアプローチこそが、組織の持続可能性を高める唯一の方法だ。
まとめ|正論の力を「対話」に変える時代へ
「正論が通じない」という課題に直面したとき、怒るでも、嘆くでもなく、まずは“伝え方”を変えるべきである。経営とは、正しさを押し付けることではない。対話を通じて、組織全体の納得と行動を引き出す営みだ。
正論を「対話の起点」に変えることができれば、経営者としての発言力は何倍にもなる。今後は、正論を通す力よりも、“正論を通じる言葉に変換する力”こそが、組織を前に進める最大のスキルとなる。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。