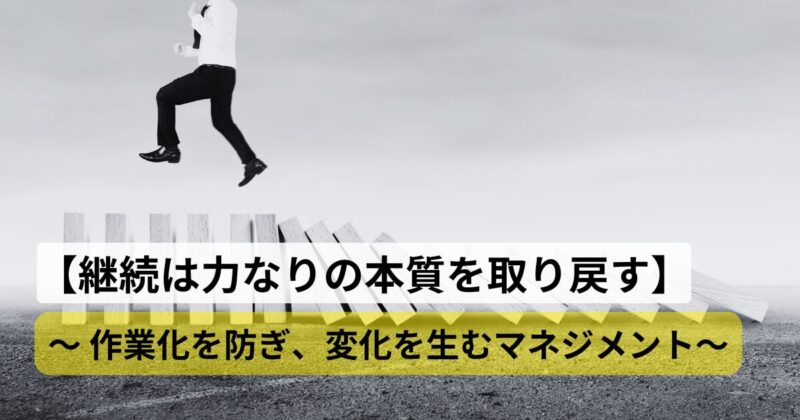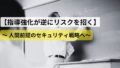「継続は力なり」とよく言われるが、ただ続けることに満足してしまえば、それは“作業”に堕してしまう。中小企業の現場では、ブログ更新、社内イベント、定例会議などが“やっていることに意味がある”と錯覚されがちだ。実際には、それらがどんな“変化”を生み出しているのかを問わなければならない。本稿では、「継続=変化を生む器」と再定義し、継続施策を“成果が出る構造”に変えるための視点と設計を提示する。キーワードは「変化KPI」と「やめどき設計」である。
継続が「力」になる条件/ならない条件
継続が力になるには、前提として「仮説」「検証」「更新」が仕組み化されている必要がある。逆に、やること自体が目的化してしまうと、組織の力を奪う存在になる。

力になる継続=学習の累積
意味のある継続とは、目的の明確化と成果指標をもとに仮説検証を重ねるものだ。たとえば社内勉強会が「若手社員の提案力向上」を目的に設計され、参加者のアウトプット数や改善案の採用率を追っているようなケース。これは継続するほどに学びが蓄積される仕組みであり、力となる。
力を奪う継続=手段の目的化
一方で、「毎週やっているから」「昔からあるから」などの理由で続いている会議やイベントは、しばしば目的を見失っている。たとえばブログ更新も、“更新すること”がゴールになってしまえば、それは誰にも届かない作業にすぎない。こうした継続は、時間とリソースを静かに消耗させる。
見分ける3つの指標
継続が“力”か“負担”かを見分けるには、以下の3つの指標で点検する。
- ①変化の有無(成果・行動・状態が更新されているか)
- ②やめどきの明示(廃止・変更の基準があるか)
- ③目的の共有(実施者・関係者が意図を説明できるか)
「ただ続ける」心理を分解する
定例会、イベント、ルーティン業務、ブログ更新…。
やめ時がわからず、つい惰性で続けてしまうことはないだろうか?
でもこれは、“怠慢”や“思考停止”ではなく、人間が持つ健全な心理反応とも言える。
責めるべきは人ではなく、「変えにくい構造」そのものである。
安心感への依存:続いているだけで“日常”が守られる
長く続けてきたことには、「安心の装置」としての役割がある。
たとえば、毎週の朝礼や月例の飲み会。業績に直結していなくても、「今月もやれた」という事実が、心の安定になっている。
変化にはエネルギーがいるし、「このままでいいのでは」という空気は、居心地がいい。
特に忙しい現場では、目の前のタスクで手一杯になりやすく、変化の余白が見つけづらい。
だから、あえて言おう。
「安心したくて、続けてる」それって、実はごく自然な反応だと。
問題なのは、安心のまま止まってしまうこと。
安心に寄りかかるのではなく、安心を足場に“次のステージ”へ動く構造を仕込めるかどうかがポイントになる。
一貫性バイアス:「今までの努力を無駄にしたくない」
こんな場面、経験がないだろうか?
「この取り組み、あまり成果出てないですよね…」
「でもさ、ここまでやってきたし…もう少し様子見よう」
やめたら「今までの努力が無駄になる」と感じてしまうこの心理は、一貫性バイアスと呼ばれる。
実はこれ、自己防衛の一種でもある。人は、「過去の自分」を否定したくない。
「3年間、続けてきたこと」に対して「もう意味ないからやめよう」とは、なかなか言いづらい。
しかし、本当に大切なのは「継続したかどうか」ではなく、
「その継続が何を生んだか」「これから何を生むのか」だ。
むしろ、惰性をリセットできる決断こそ、過去の努力を無駄にしない方法とも言える。
だから「やめる」は敗北ではなく、「一貫した成長のための決断」と捉える視点が必要になる。
所属のニーズ:「場があるだけで安心する」という感情
特に飲み会、社内イベント、懇親会などにありがちなのが、「参加することに意味がある」とされる構造。
実際、そこに集まることで「自分はこの組織の一員だ」という実感を得ている人も多い。
何をするでもないが、“場にいるだけで救われる”という人は少なくない。
この心理は悪いものではない。人は、どこかに“属したい”という欲求を持っている。
しかし、所属の意味を「ただ参加していること」で満たそうとすると、継続の目的が曖昧化する。
結果として「何を得たか」ではなく、「参加できたかどうか」だけが残る。
だからこそ、「つながりたい」という感情自体を否定せず、
その上で“所属しながらも何かが変わる設計”を持たせることが重要なのだ。
成果定義の曖昧さ:良さそうだけど、何が良いかよくわからない
「これ、まあまあ評判良いし、なんとなく続けよう」
「直接の成果はないけど、雰囲気は悪くないよね」
この“なんとなく良さそう”という状態も、惰性を生む温床になる。
なぜなら、成果が明確に定義されていないと、良し悪しの判断ができないからだ。
評価されず、改善もされない。
やめ時も見つからないまま、「一応やっとこうか」が続いていく。
ここで必要なのは、「何をもって成果とするか」を、たった1つでもいいから数値や行動で定義すること。
たとえば:
“ふわっとした良さ”を可視化しない限り、継続は自己満足に終わってしまう。
小さな設計変更で、人は“変われる”
人が変化を避けるのは、心理的な弱さではなく、構造の欠如によるもの。
続けることに安心するのも、一貫性を守ろうとするのも、場に属したくなるのも、人として自然な反応である。
だからこそ、心理を否定するのではなく、自然な反応が“前進”につながるような設計を仕込むことが肝要だ。
仕組みがあれば、人は変われる。
変われれば、継続は意味を持つ。
そしてその継続が、成果を生み始める。
惰性を価値に変える設計:4ステップ
継続を変化の源泉に変えるための設計は、以下の4ステップで整理できる。
①目的を“誰の何をどう変えるか”で書き換える
「なんのために」ではなく、「誰の、どんな行動や状態を、どう変えるか?」という問いに変えることで、抽象的な目的が具体化される。
②成果仮説を数値化する(変化KPI)
「参加者の満足度」ではなく、「初参加者が3人以上と対話できたか」「その後アポにつながったか」など、行動の変化にフォーカスしたKPIを1つだけ設定する。
③運営を小さく実験する(90日で形式見直し)
“やってみる”スタンスで開始し、90日後に「Keep/Improve/Stop」でレビュー。変化が見られない場合は形式変更を前提とする。
④やめどき基準を決める
「3回連続でKPI未達成なら形式変更」「参加者数が半減したら一時休止」など、事前に“やめどき”を合意しておく。これにより、無意味な継続が抑止される。
ケーススタディ:定例会議を“変化の場”にアップデートする
課題:
毎週開催されている定例会議。出席率は高いが、会議後に「で、何が決まったんだっけ?」という空気が漂う。
「先週と同じ報告」「資料を読めば分かる内容の読み上げ」「責任が曖昧なToDo」…
このような“会議あるある”が積み重なり、時間と人件費だけが消耗されていく構造になっていた…
見直しの起点:変化が生まれていない事実
実態調査をしてみると、次のような“気づき”があった。
- 議事録は残っているが、次週に誰も読み返していない
- 発言は報告中心で、提案や疑問がほとんど出ていない
- アクションが「検討する」「調整する」など曖昧な言葉に終始
- 会議に参加しているのに、Slackやメールで並行作業している社員も…
つまり「会議=業務進行の必須インフラ」ではなく、「とりあえずやるもの」「参加してるだけで仕事した気になれる場」になっていた。
設計変更:3つの具体アクション
この状況を打開するために、以下の設計変更を加えた。
① 開始3分ルール:「前回から何が変わった?」を必ず聞く
冒頭に、各自が「前回の会議以降、自分の領域でどんな変化があったか」を報告する。
“進捗”ではなく“変化”に焦点を当てるのがポイント。
Before:「資料はまだ途中ですが、今週中には仕上げます」
After:「前回までは顧客の反応が薄かったが、価格の表現を変えたことで問合せが増えた」
こうすることで、「継続している施策が、何を動かしたか?」という評価軸が会議に持ち込まれる。
② アジェンダに“未設定議題枠”を設ける
定例会議のアジェンダは固定化しやすく、「いつもの報告」で埋まってしまう。
そこで、最後の10分を“空白時間”として確保し、参加者がその場で出した「今週感じた違和感」「小さな課題提案」などを共有する場にした。
たとえば以下のような声が出た:
- 「最近、受注後のやりとりでミスが増えてる気がする」
- 「この資料、毎週作ってるけど誰か読んでる?」
- 「〇〇業務、手間に対して成果が見合ってないかも…」
この“未設定枠”があることで、現場に埋もれていた違和感が表に出てきた。全員が“自分事”として議題を持ち寄れるようになった。
③ 終了前にKISチェック(Keep/Improve/Stop)
会議の締めくくりに、参加者全員が30秒以内で一言発言するルールを設定。
- Keep:次回も続けたいこと(例:「未設定枠の話、すごく良かった」)
- Improve:改善したい点(例:「次回はもっと数字で話そう」)
- Stop:やめてもいいと感じたこと(例:「この議題はもう形骸化しているかも」)
ここで「やめる勇気」が言語化されることが重要だった。
“やること”の決定だけでなく、“やめること”も議論の対象にすることで、継続の質が自然と上がっていった。
効果:会議に“エンジン”がついた感覚
3ヶ月の運用で、明らかな変化が表れた。
- アジェンダの8割が“報告”から“意思決定”に変化
- 会議後、Slackでの共有・提案が2倍以上に増加
- アクション数が増えるだけでなく、達成率が向上
- 毎週“なにかが前に進んでいる”という実感が可視化された
参加者からは「参加する意味を感じるようになった」「会議が“動く場”に変わった」という声が上がり、実質的な生産性が向上した。
ポイント:小さな仕組みが会議を“変化の場”に変える
このケースで重要だったのは、会議そのものを否定したわけではない点。
あくまで、「会議を通じて何を変えるのか?」という視点を持ち込み、継続の構造を再設計したことにある。
- 変化にフォーカスする問いを仕込む
- 意見を引き出す余白をあえて設計する
- 評価を言語化し、小さな改善を積み上げる
これらの仕組みはコストもゼロ。誰でも明日から始められるが、会議の意味を根本から変える“レバレッジ”になる。
まとめ|会議も継続も「設計」しなければ変化は起きない
継続とは、単に続けることではない。変化を生む仕組みを組み込んだとき、初めて意味を持つ。
今回の定例会議の事例のように、「変化KPI」「空白の議題枠」「やめどきの言語化」といった設計を導入することで、日常業務は“変化の連鎖”へと進化する。
継続=小さな設計変更の連続
これが「継続は力なり」の本質的な意味と捉えることで、今やっていることの見え方が変わってくるのではないだろうか。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。