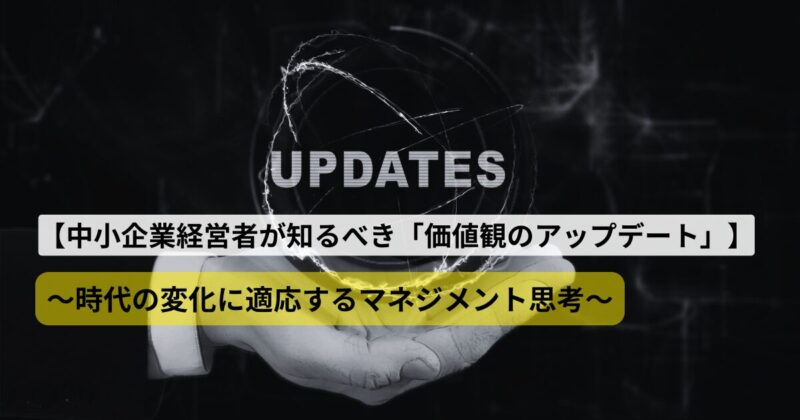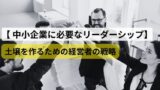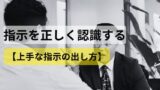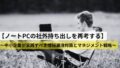中小企業経営者が長年培ってきた経験や成功体験は貴重であり、企業経営の礎として尊重されるべきものである。しかし、ITインフラや働き方、多様性に対する社会的認識の変化が加速する現代において、その過去の価値観が必ずしも今の時代に通用するとは限らない。
パワハラ・ハラスメントへの感度、ダイバーシティやLGBTQへの理解、さらにはIT活用における世代間ギャップ…。これらに無自覚なままでは、社内の信頼関係は築けず、社員の離職や組織の硬直化を招くリスクがある。本稿では、経営者自身が価値観をアップデートし、変化に対応するための視点と行動指針について、マネジメントとインプットの重要性を軸に考察する。
価値観のアップデートが求められる時代背景
現代のビジネス環境は、かつての常識が通用しなくなるほどのスピードで変化している。中小企業の経営者が過去の成功体験に固執することは、経営リスクの一因となりうる。
昔の常識が「パワハラ」になる時代の変化を直視する
少しの注意や指導が「パワハラ」認定される社会。飲み会の強要や業務上の厳しい指導が、コンプライアンス違反とされるケースが増えている。これは単なる世代間ギャップではなく、社会全体の価値観が変わっている証左である。にもかかわらず、「俺たちの時代は…」という言動が続けば、社員との信頼関係は築けない。変わったのは「人」ではなく「環境」なのだ。

IT環境と情報格差が生むジェネレーションギャップ
スマホやAIとともに育ってきた若手社員は、旧来の手法に馴染みがない。「努力して覚えろ」では通じないこともある。それに対し、ベテラン経営者は過去の経験を基に「できるはずだ」と期待してしまいがち。だが、その期待は往々にして一方的であり、実際の業務成果にはつながらない。「できない理由」ではなく、「やり方を知らない」というギャップを埋める視点が求められる。
多様性の受容と“主観的正義”の危うさ
LGBTQやダイバーシティといったキーワードがビジネスの現場でも当たり前となりつつある今、経営者の言動ひとつが信頼を損なう原因になり得る。「そんなのは昔からあった」「男女は違うんだから平等なんて無理」などの主観は通用しない。必要なのは「背景を知ること」「定義を理解すること」である。感情論ではなく、知識に裏打ちされた言動が求められる。

定義と歴史を知ることが経営者の信頼につながる
「変化に対応しろ」「多様性を受け入れろ」と言われても、経営者にとっては“なぜ”そうなのかが腹落ちしなければ、行動に結びつかない。その“なぜ”を紐解く鍵が「定義」と「歴史」である。
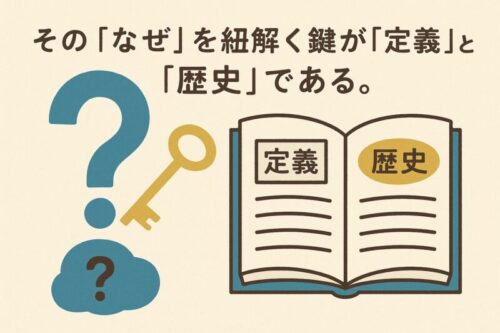
“有給休暇”の定義から見える時代の変化
有給休暇は、もともと社員の体調不良や私的な事情を考慮し、企業が労働に対する対価を「信頼の証」として支払う制度である。しかし現在では「消化しないと損」「旅行のために使うもの」として認識されている。このような価値観の変容は、制度の本質を知らないまま使われていることに起因する。経営者自身が定義と成立過程を理解することで、制度の運用方針に説得力が生まれる。
「言葉の定義」がなければ議論は迷走する
「平等」「成果主義」「働き方改革」など、使われる言葉には必ず“定義”がある。これを知らずに自分の感覚で使うと、部下との間で誤解や反発を招く。たとえば、「チャレンジを評価する」という制度も、何をもって“チャレンジ”とするかが曖昧であれば評価はできない。
経営者は「定義」を学ぶことがリーダーシップの土台となる
リーダーシップとは、正論をぶつけることではない。相手の背景を理解し、共通の土台=定義をもとに会話をすることが出発点である。定義を知らなければ、議論は主観のぶつかり合いになり、建設的な議論はできない。
インプットの質がアウトプットの質を決める
経営者は常に学び続けなければならない。だが、何をどう学べばよいのか?という問いに対して明確な答えを持っている人は少ない。
成功体験ベースの思考から抜け出すために
「俺の経験では…」「昔はこうだった…」と語る経営者は多い。だが、それは過去の成功体験に基づいた“主観的正解”に過ぎない。時代が変われば成功法則も変わる。だからこそ、今のビジネスに必要なのは、経験ではなく「視点を更新する力」だ。
読書やセミナーではなく“定義”を読む訓練を
自己啓発書やビジネス書は多く存在するが、それらを読んだだけでは経営の本質は学べない。必要なのは、物事の「定義」を読み解き、その背後にある歴史や社会背景を知る力である。それにより、自分の意見に「意味の裏付け」が生まれる。
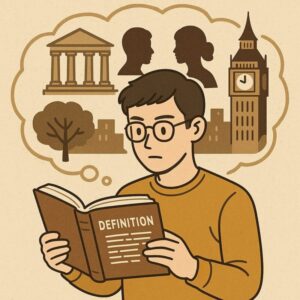
インプットがなければ、社員に“発信”する資格はない
社内でリーダーとして語る立場にある経営者が、学んでいないと見抜かれる時代になった。社員はネットやSNSで大量の情報に触れており、経営者の発言が薄っぺらければすぐに見透かされる。逆に、背景や理由を持って語れる人間には信頼が集まる。
まとめ:過去の成功体験から脱却せよ
中小企業の経営者に求められているのは、今を生きる社員や社会の価値観と真摯に向き合い、自らの言動をアップデートし続ける姿勢である。過去の成功体験や常識に頼るのではなく、「なぜそれが求められているのか」「その定義は何か」「どのような経緯で形成されたのか」を知り、そこから物事を語れる力が必要だ。
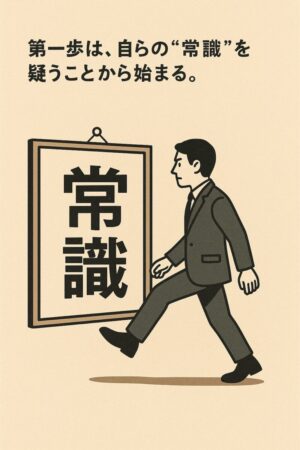
そのためにはインプットの習慣化が不可欠であり、同時に経営者自身の意識改革が求められている。経営者が変われば組織も変わる。その第一歩は、自らの“常識”を疑うことから始まる。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。